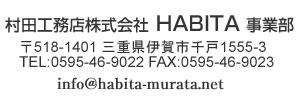幸いにもわが国の先人たちは、多くの木材資源を残してくれました。戦後に植えられた樹齢60年の国産材として育っているのです。
一本一本の年輪が積もり、毎年9,000万m3の木材が増加している中で、国産材供給量は2,000万m3に過ぎません。
しかもその多くは人工林です。木は地球温暖化の原因とされているCO2を固定化させる貴重な環境資源です。しかも伐採され加工された後もCO2を保持し続けます。つまり長期耐用の木造住宅はCO2を貯蔵する第2の森でもあるのです。
HABITAの提案する大断面木構造の住まいづくりは環境保全のためにも、日本で育ったこの価値ある樹木の価値を活用してゆきます。 |
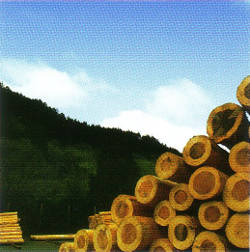 |